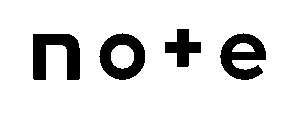ソーシャルメディアを題材としながら,企業や団体と消費者の関係性について研究しています。
専門はマーケティング論・ソーシャルメディアマーケティング戦略(SMMSs)。
麻里 久
Hisashi Mari
福井工業大学
経営情報学部 経営情報学科
大学院 工学研究科(社会システム学)
AI&IoTセンター
准教授
立命館大学
OIC総合研究機構
客員研究員
静岡大学情報学部卒業後,JR東海エージェンシー,博報堂にて広告コミュニケーションを中心とした企業・団体のマーケティング支援業務に従事。食品・飲料・日用品・金融・教育・BtoB・自治体・官公庁等幅広い業種を担当。業務の傍らで大学院に進学し,首都大学東京(現東京都立大学)大学院社会科学研究科博士前期課程を修了(MBA,修士(経営学))後,東京都立大学大学院社会科学研究科博士後期課程を修了。博士(経営学)。2025年度より現職。
主な著作に「ソーシャルメディアはブランドコミュニティか,ブランドパブリックか? ― 企業公式Facebookページの分析 ―」(マーケティングジャーナル2020奨励賞),「企業公式ソーシャルメディアアカウントのアイデンティティ形成」(商品研究),「広告的,関係性マーケティング再考」(JAAA 第49回懸賞論文「私の言いたいこと」一般部門 入賞)などがある。
日本マーケティング学会 マーケティングジャーナル アソシエイトエディター,リサーチプロジェクト AI研究会 企画運営メンバー。
所属学会:日本マーケティング学会,日本消費者行動研究学会,日本商業学会,組織学会,日本商品学会,日本広告学会(入会順)
研究哲学
The philosophy of research
実践的,観察者。
マーケティング論(市場戦略論)は,企業などの組織が実際に行っている活動の現場を主たる関心の対象とし,それらを観察することから出発する学問です。私たち研究者は,実務家の実践や消費者の行動・意識を観察し,そこから理論を構築していきます。その目的はアカデミア(学術)の発展にありますが,マーケティング論に関して言えば,何より実務への還元が強く意識されるべきだと考えています。
私は実務の世界に21年間,そして並行して学術の世界に11年間,二足の草鞋を履きながら両方のフィールドに関わってきました。その中で痛感したのは,実務と学術のあいだに存在する距離感です。実務家の中には,理論を机上の空論と見なしたり,学術的な研究を現実の後追いにすぎないと感じる方もいます。しかし,理論を実際のビジネスに応用してきた立場からすると,そうした見方は誤解であり,社会にとって大きな損失だと感じます。
経営学者の宇田川元一先生の言葉を借りれば,学術的な研究とは「対象に対して少し距離を持ち,日常的な有用性とは異なる角度から観察し,そこから分かったことを学問体系を活用して構造化していくという実践」であるとされます(宇田川, 2025)。少なくとも経営学においては,実務と学術は本来切り離されるべきものではなく,学術的な研究もまた実務的な実践の一手段たり得るものだと捉えています。
実務家出身の研究者である私の使命のひとつは,理論と実践の往還を実現することにあります。理論の構築には,プロパーの研究者に及ばない部分もあるでしょうし,現場での実践においては,現役の実務家には敵わないかもしれません。だからこそ,私は両方のフィールドを行き来し,実践を観察して理論を構築し,それを実務へと翻訳・応用し,さらにその実践を観察して次の理論へとつなげる——この連環をつくることこそが,私にしかできない価値創出のあり方であり,私が社会に提供することが出来る貢献の形であると考えます。
研究者として目指す姿
My ideal
– 圧倒的,観察。
- 圧倒的な市場観察 … Fieldwork (Including Netnography by Kozinets)
- 圧倒的な理論観察 … Literature Review
- 市場観察×理論観察により理論と理論に基づく実践的インプリケーション(打ち手)を生み出す
– “理論”を通じた観察を行い,”理論”を通じて現実を語る
– 常に,問い直す,という姿勢
提供する価値
Value Proposition
企業・自治体の方に向けて
ソーシャルメディア(SNS)を活用したマーケティング戦略の立案において,共同研究,調査設計支援,アドバイザリーなどのかたちでご一緒させていただくことが可能です。生活者理解やマーケティング理論をベースとした長期的な視点から,実践的な施策に対する支援を行います。
大学生・高校生・保護者の方に向けて
講義や演習・実習,卒業研究を通じて,マーケティングに関する「活きた知識」と「現場で活かせるスキル」を身につけていただくことができます。加えて,他者を想像し,協働し,理論的に考え抜く力,議論し,伝える力を育む教育を目指しています。学びの中で,社会と向き合う自分の軸を育んでほしいと願っています。
大学院を志望する社会人の方に向けて
実務への還元が主たる目的であると推察しますので,できる限りその要請にお応えしたいと思います。ただし,その実現方法については少し期待とは異なるかもしれません。私が共感するこちらの記事をご一読いただけますと幸いです。もちろんより実務に近い学びを得たいという方や研究職を目指したいという方も歓迎いたします。
メディア・地域の方に向けて
ソーシャルメディア(SNS)やマーケティングをテーマにした講演・記事執筆・取材対応を行っています。ご関心をお持ちいただけましたら,お気軽にご相談ください。地域企業との連携や教育現場での出前授業なども対応可能です。
研究関心
Research interests
消費者市場における関係性マーケティング
Relationship Marketing in Consumer Market
売り手と買い手の数が少ない産業財や直接相対して相互作用が生まれやすいサービス財については研究が発展していますが,流通業者が介在することの多い消費者市場における関係性マーケティングは未だ未開拓の領域です(Sheth, 2015; Mari, 2017)。しかしながら,今日においては,情報通信技術(ICT)の発達により,消費者市場にも変化が見られます。かつて分断されていた売り手と買い手が再び相対し,相互作用が生まれやすい環境が生まれつつあります。そのような状況を踏まえて,改めて,企業や団体と消費者の相互作用と関係性に目を向け,この領域の発展可能性について議論していきます。
ソーシャルメディア・マーケティング戦略
Social Media Marketing Strategy (SMMSs)
企業や団体と消費者の相互作用と関係性について,今,一番注目を集めているもののひとつがソーシャルメディアです。もはやソーシャルメディアを抜きにして企業や団体はマーケティングを行うことが難しくなってきていると言っても過言ではないと思いますし,少なくとも(やるかやらないかは別として)ソーシャルメディアを視野に入れたマーケティング戦略の立案が一般的なものになってきていると感じます。しかしながら,実務においては果敢な実践的挑戦が試みられているものの,理論化や知見の体系化はまだまだ遅れています(世界的にはここ数年でかなりの進展がみられます)。そこで,まずは理論の体系化と実務的なインプリケーションの導出を目指します。また,とりわけ未開拓な領域となっているのが企業・ブランドと消費者の相互作用と関係性です。私の関心では,特にこの点に焦点を当てながら,さまざまな研究プロジェクトを進めています。
ブランドコミュニティ&ブランドパブリック
Brand Community & Brand Public
ソーシャルメディアの登場により,より注目を集めることになったのが「ブランドコミュニティ」という概念です。Muñiz and O’Guinn(2001)は,これまで血縁や地縁が基盤となって形成されてきたコミュニティが,その基盤を超越し,ブランドという現代消費の象徴とも言える概念を基盤としながら形成されていることを明らかにし,これをブランドコミュニティと呼びました。彼らが描き出すブランドコミュニティにおいては,ブランドを核として自発的に凝集し,相互に作用し合う消費者たちの姿が描き出されています(Muñiz and O’Guinn, 2001)。これに対して,Arvidsson and Caliandro(2015)は,ソーシャルメディアではメンバー間の相互作用や同一性が重んじられるブランドコミュニティとは異なり,互いに対話することはないが,とりとめのない共通の関心によって構成され,多様な視点や経験が許容される新たな場が見られるとしてこれを Tarde(1901)が示すパブリックの概念に倣ってブランドパブリックと呼びました。ソーシャルメディアにおいては,いずれもあり得るというのが今のところの私の結論ですが,どのような時にコミュニティを形成し,どのような時にパブリックを形成するのか,そして企業や団体・消費者,双方にとってどのような価値を生み出しているのかについてはまだまだ不明瞭な部分が多く存在しています(Mari, 2020)。これらを明らかにしていきます。
消費者文化理論
Consumer Culture Theory (CCT)
手掛かりとなるのが,消費者の行動,市場,文化的意味の間のダイナミックな関係を扱う理論的視点である消費者文化理論(CCT; Consumer Culture Theory)(Arnould and Thompson, 2005)です。CCTが示す,消費を文化的・象徴的な実践として捉えるこのような視座は,企業や団体と消費者との関係性を考える上で示唆に富んでおり,現在この枠組みから学びを得ながら,自身の研究にどう取り入れられるかを模索しています。とりわけ,消費が私たち生活者にとってどのような意味をもち,組織側がそれにどう応答しているのかという「インタラクティブな意味のやりとり」に関心を持っています。
ネトノグラフィー
Netnography
研究手法としては,消費者意識調査・購買行動調査といったデータを統計学的に取り扱う定量的な実証研究にも取り組みますが,消費者文化理論に関心を寄せているところからもわかるように,定量データだけでは明らかにすることが困難な人間の「消費」という営みを,豊かな記述と解釈により明らかにする解釈主義的な定性アプローチを取ることを好んでいます。近年,特に注目して取り組んでいるのがKozinets(2010, 2015, 2020)が提唱するネトノグラフィー(Netnography)という手法です。ソーシャルメディアに棲み込み,時に参加し,時に観察する,エスノグラフィック的なこのようなアプローチを実証研究と組み合わせることにより,人間味溢れる,社会や人間に寄り添った理論の構築を目指しています。